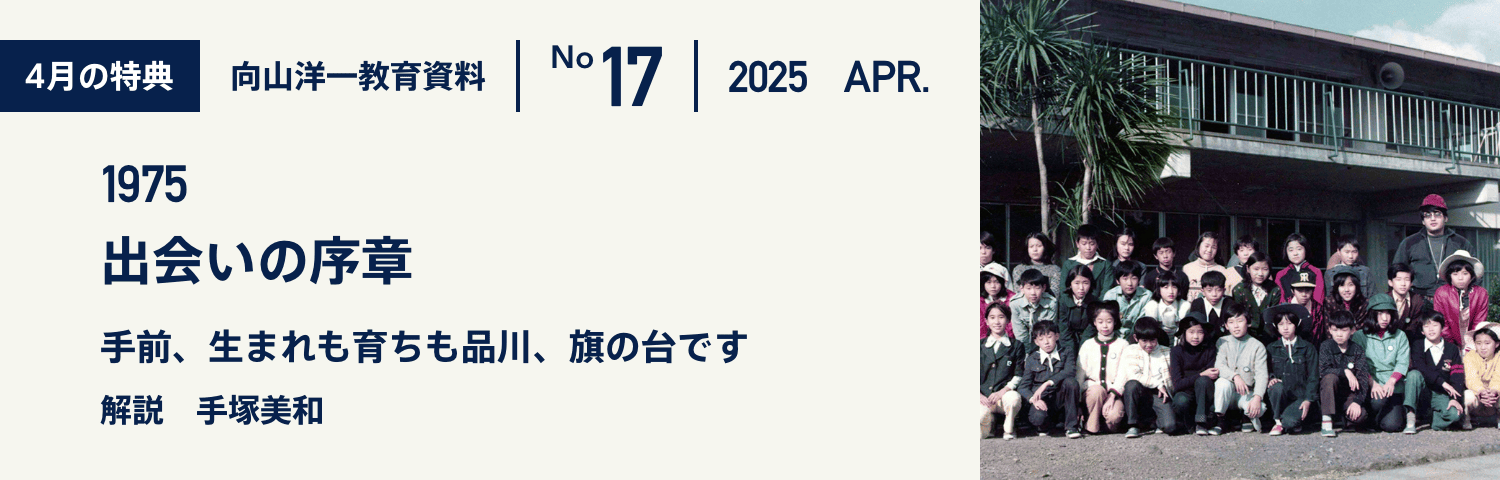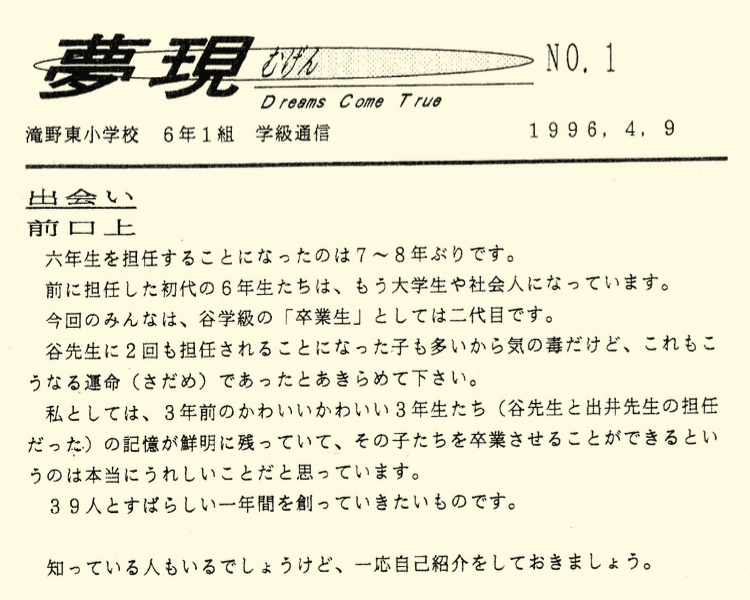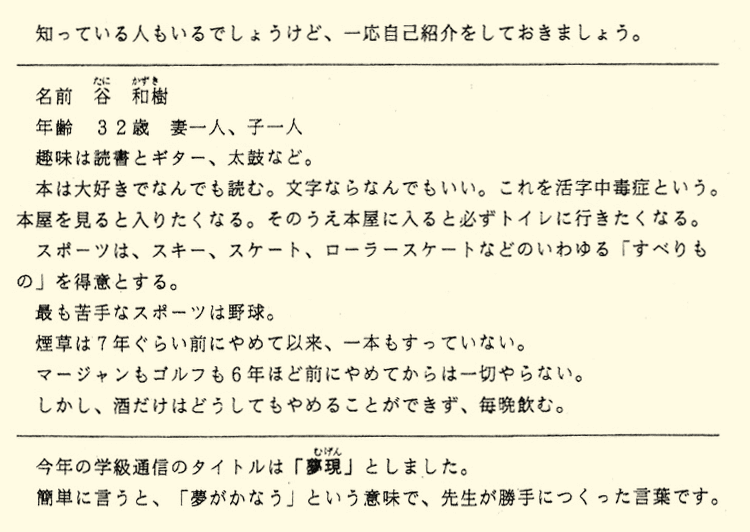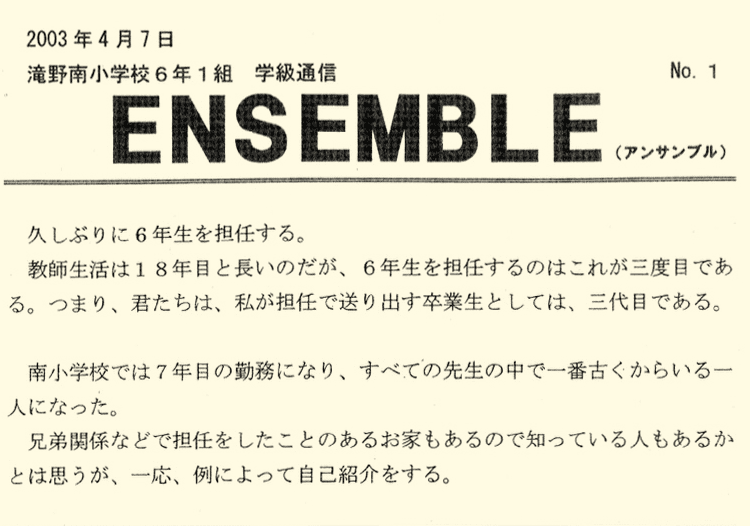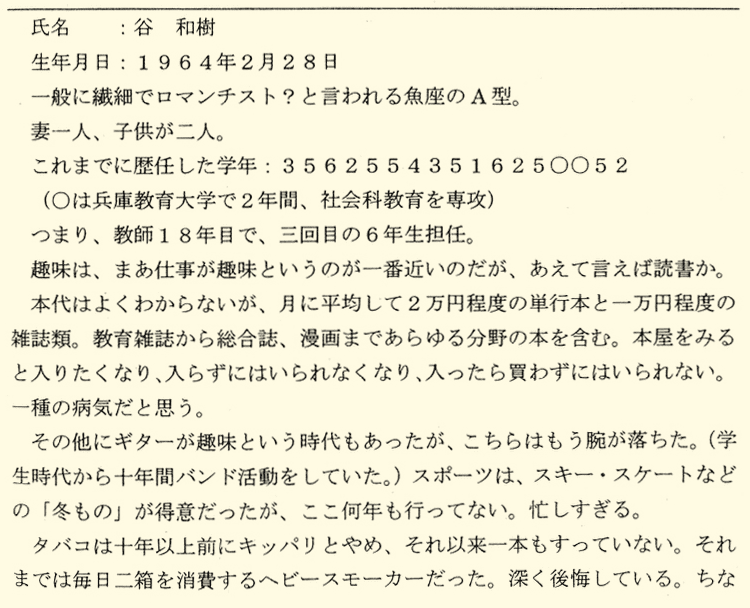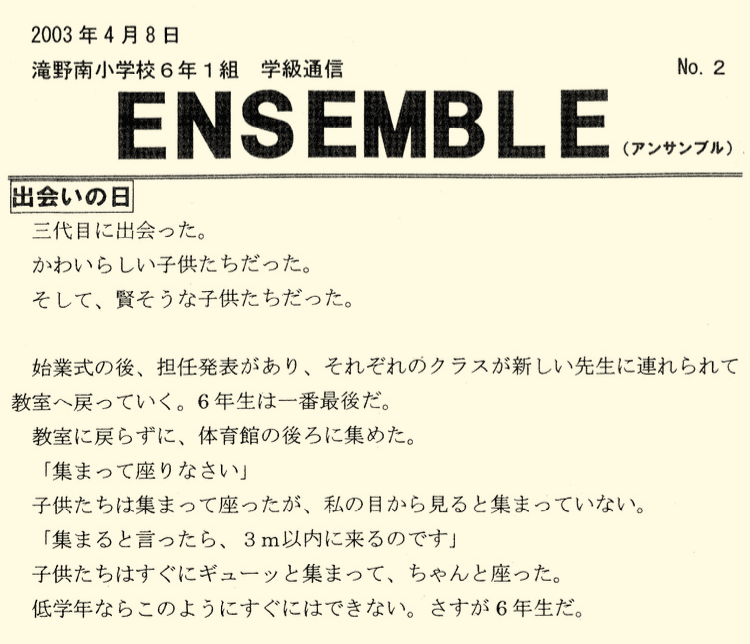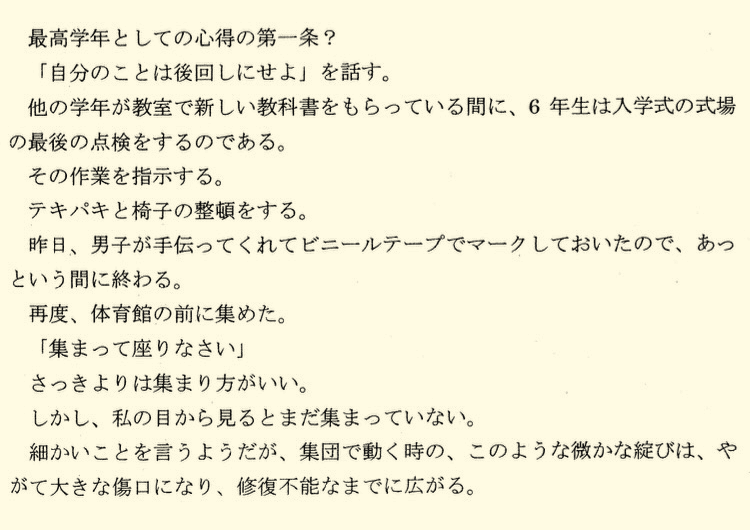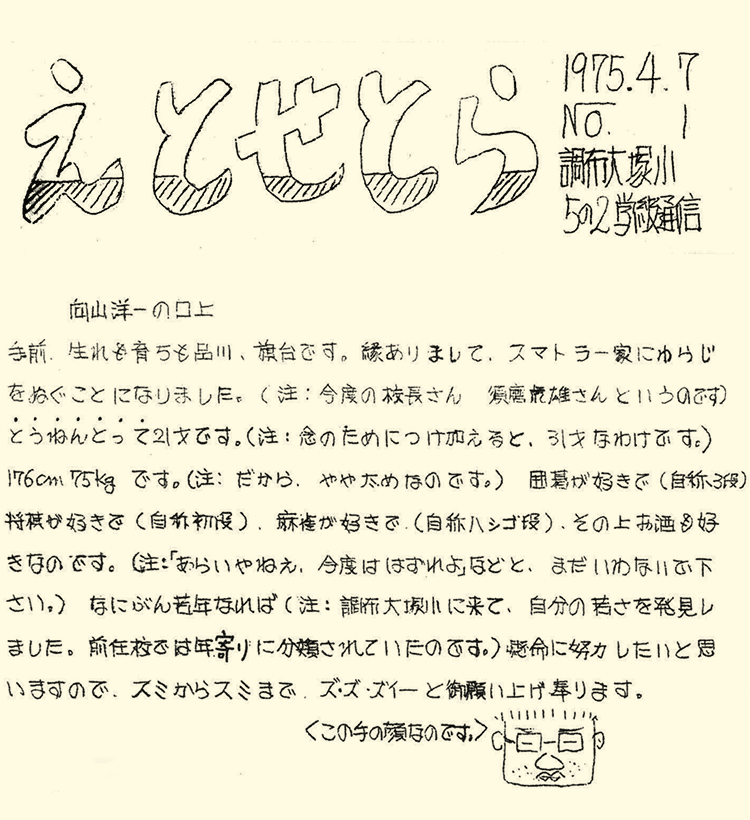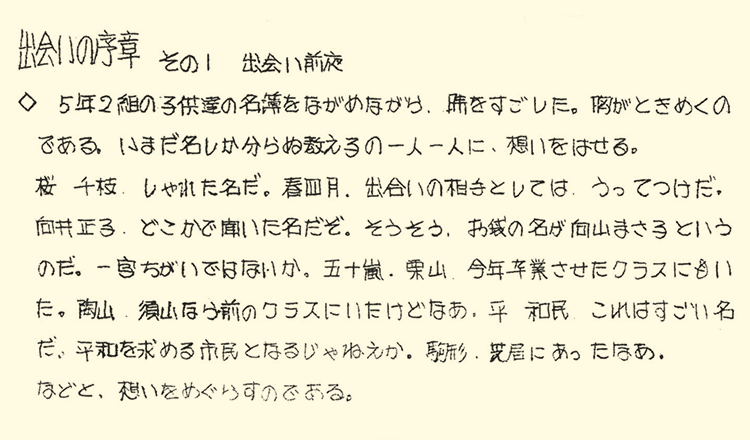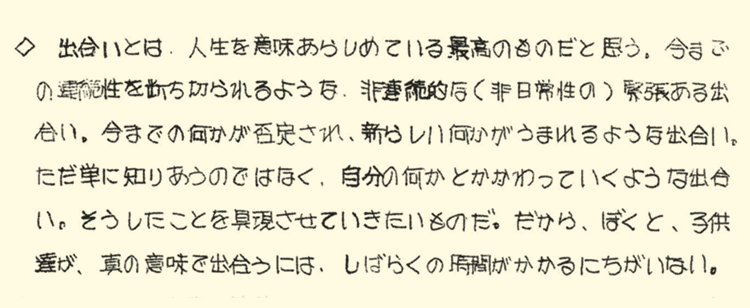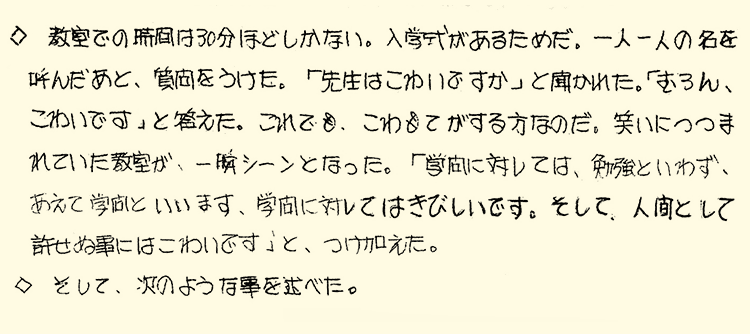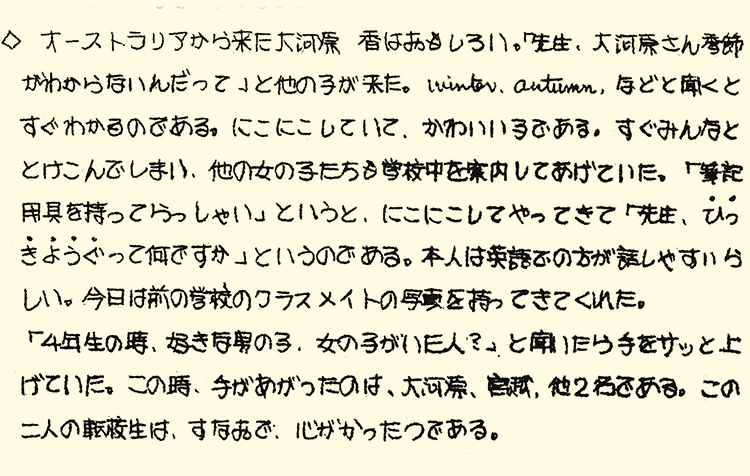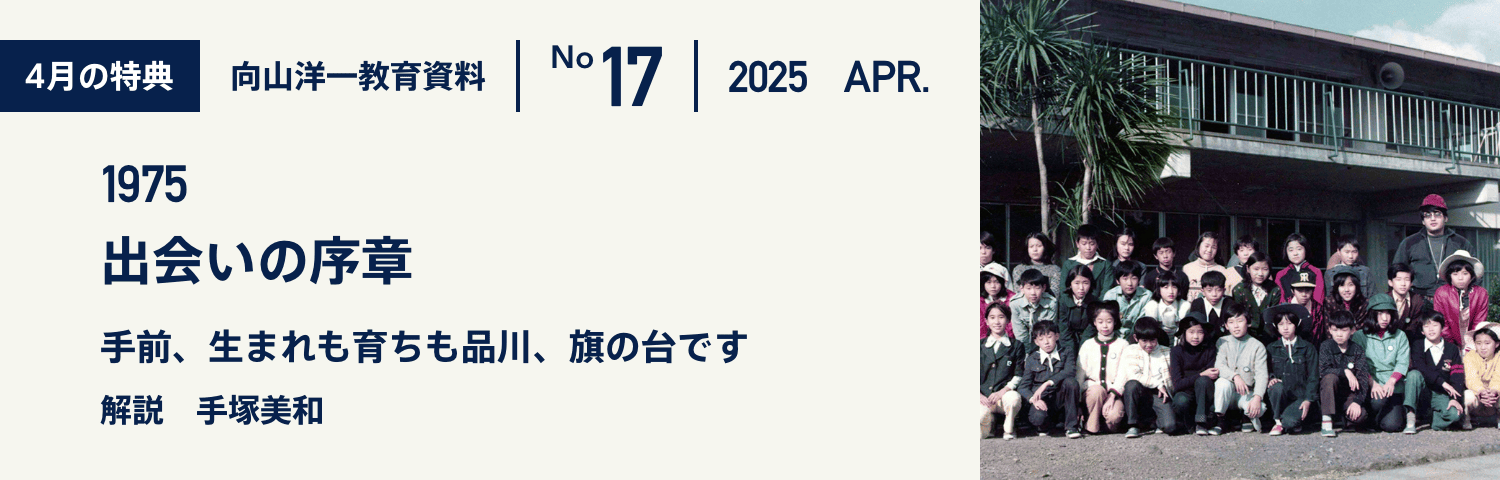
谷和樹の解説
| 出会いの序章 |
 |
学級通信の書き方。
向山の影響を強く受けました。
強く受けたんなら、もう少しマシに書けよ。
はい。
自分でもわかってます。
おそらく、
|
|
「カタチ」だけ
|
マネしたのでしょう。
表面的です。
だから、実質がともないません。
実質って?
それは、
「授業力」とか
「学級経営力」とかです。
ですが、本当は
|
「知性のバックボーン」とか
「通ってきた修羅場」とか
|
そういうのだろうな。
それが違うんだよなって思います。
それが
「筆力」に出ます。
迫力が違うんです。
先週のメルマガ。
1993年の私の学級通信を紹介しました。
今週もいくつか、
向山の影響を受けてるっぽいのを、
紹介してみましょうね。
性懲りもなくですが。
まず、1996年の6年生。
私は32歳でした。
今から思えば青二才です。
それでも、教師11年目。
このときの6年生は、私にとって特別でした。
|
|
初めて納得できた1年間
|
|
だったからです。 |
精一杯やった。
本当に全力を出し切った。
もうこれ以上は絶対にできなかった。
|
そう確信できた1年間だったのです。
向山が書くところの
|
教師の勲章は、
燃えて燃えて燃え尽きた朝に訪れる
透明な冷気である。
(向山洋一「スナイパー」No.91)
|
という感覚が、ちょっぴり分かり始めた年でした。
その年の学級通信の創刊号。
|
|
この学年は3年生でも担任していました。
先週紹介した『じゃりんこ』の学年です。
「前口上」
という書き方が、そもそも向山のマネですね。
前口上にしては、いまいちですが。
このあと「自己紹介」が続きます。
|
|
これくらいでいいでしょうか。
これが、2003年の6年生になると、少し変化します。
私の三代目の6年生です。
私は39歳。
6年担任かつ、研究主任かつ、教務主任でした。
|
|
まず、学級通信のタイトルが「アンサンブル」ですね。
もちろん向山の
「アンバランス」
「エトランゼ」
「エトセトラ」
などに影響を受けたタイトルでしょう。
ちなみに、向山の学級通信のタイトルは
「ア行」
から始まるのが、やや多いんですよね。
「アチャラ」
とかね。
向山は「辞書」を最初から引きながらタイトルを考えたからだ、と読んだことがあります。
私もそれをマネしたのでしょう。
このときの自己紹介。
こんな感じになっています。
|
|
いやー。
今読むとやはり恥ずかしいですねー。
書いてあることは事実なので、しかたないですが。
このアンサンブル2号には出会いの日の描写もあります。
|
|
向山のマネをして、なんとか描写的に書こうとしたのでしょう。
その努力のあとだけは伝わってきます。
|
|
未熟とはいえ18年目です。
まあ何か、勢い?のようなものは伝わってきますね。
自分で言うのも何ですが、
この頃の私は、学校では
「自信満々」
でした。
TOSSのセミナーにも登壇していました。
「フラッシュ」という技術で授業をつくったりしました。
「日本のシーレーン南沙諸島」
「地球の歴史」
そういった授業をつくったのもこの頃です。
「誰が戦争を止められたか」の授業で向山から五段を認定されたのもこの頃です。
子どもたちの細かな動きも見えていました。
向山は |
|
しゃべりたい子は、かすかに小指が動く。
(向山洋一『新版 続・授業の腕を上げる法則』p.23)
|
と書いています。
その感覚も、分かるようになっていました。
また、考えなくても、口をついて指示が出ていました。
「遠くが見える」
「無意識に連続技が出る」
そういった上級者の感覚もつかめていた頃です。
でも、少し自信満々すぎました。
鼻につく感じもあります。
今の私なら違うな、と思うこともあります。
でも、若い教師が10年以上、
一生懸命勉強したのですから、
まあ、いいでしょうか。
|
 |
| 1 向山の「口上」 |
さて、前座はこれくらいです。
今回は向山の「出会いの序章」をとりあげます。
1975年。
向山が31歳のときのものです。
向山は「大森第四小学校」(大四小=おおよんしょう)から、調布大塚小学校へ転任してきました。
学級通信は
|
|
エトセトラ
|
です。
そのNo.1。
|
|
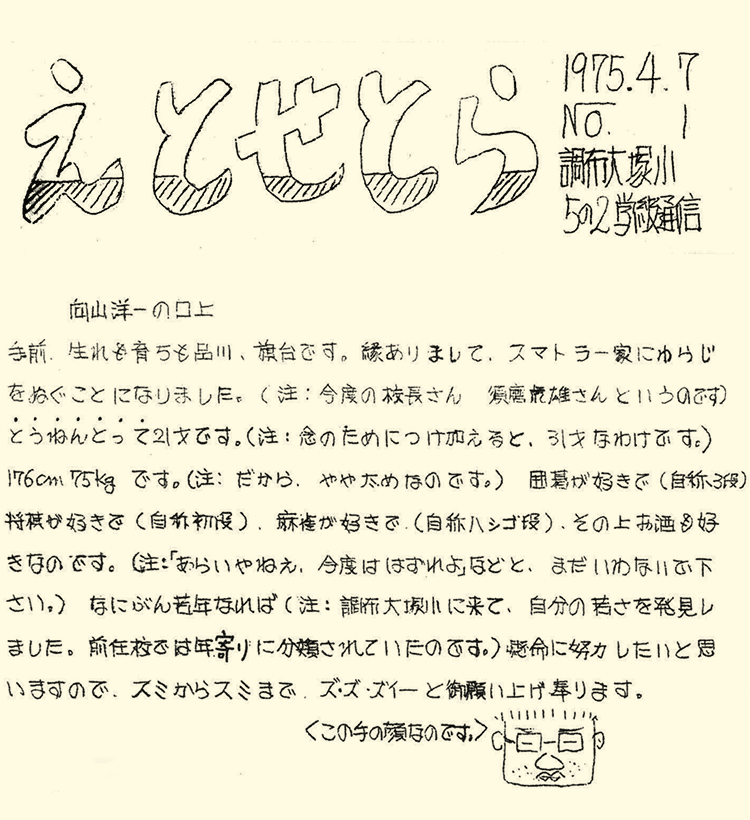
|
はい。
これこそが、「口上」ですよね。
私のは口上になっておりません。
|
お控えなすって、お控えなすって。
手前生国と発しますは江戸にござんす・・・
|
みたく始まるアレです。
向山の始まり方は「寅さん風」ですね。
|
わたくし、生まれも育ちも葛飾柴又です。
帝釈天で産湯を使い、
姓は車、名は寅次郎、
人呼んでフーテンの寅と発します。
|
ってあれです。
最後の
「スミからスミまで、ズ・ズ・ズイーと」
っていうのは、歌舞伎の座頭の口上でやるヤツですね。
いや、こういうところですよね。
さりげなく、向山の「知の厚み」が出るわけです。
当時は1975年です。
この口上が「わかる」保護者もかなりいたのではないか、と思います。
ちなみに、正進社の『話す聞くスキル』には、こういう口上が載っています。
|
1)七色とうがらし(3年)
2)ういろう売り(4年)
3)がまの油(6年)
4)南京玉すだれ(6年)
|
|
出会いで教師が口上を披露する。
学級通信にのせる。
そして教材につなげる。
そういう洒落た演出もできそうです。
|
 |
| 2 向山の「名前の覚え方」 |
| さて、「出会いの序章」本編です。
|
|
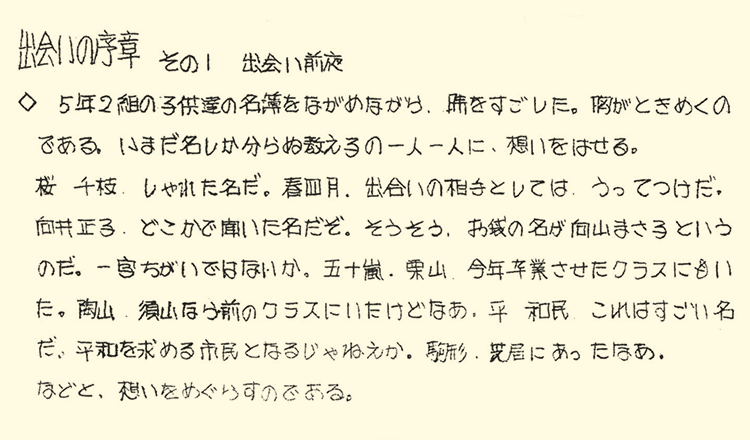
|
出会いの前夜。
向山は
|
|
「名簿をながめながら」、時をすごした。
|
と書いています。
この部分、非常に勉強になります。
|
いまだ名しか分からぬ教え子の一人一人に、
想いをはせる。
|
とありますね。
第一に
|
|
出会う前に子どもたちの名前を覚える
|
ということです。
それは向山にとっては当然のことでした。
向山の次の文章もあります。
|
初対面の時間は二十分くらいしかなかった。
一人一人の名前を呼び、立ってもらった。
名前は昨日までに覚えていた。
顔を覚えるのが今日の仕事であった。
(向山洋一『向山の教師修業十年』p.34)
|
子どもたちの名前を
「出会う前に」
覚えることの大切さ。
それはどんなに強調してもしすぎることはありません。
自分を名前で呼んでくれると人は好感を持つからです。
それも出会った初日から呼んでくれる。
その効果は計り知れません。
「出会う前に名前を覚えましょう」
私はこれを大学院の「学級経営」の講義で教えています。
毎年、必ずです。
名前の覚え方はいろいろあります。
|
1)何度も口に出して覚える。
2)何度も書いて覚える。
3)録音して何度も聴いて覚える。
|
どんな方法でもかまいません。
その人に合ったやり方で覚えればいいのです。
私は
「出席番号順の座席の位置」
で覚えていました。
座っている場所を見れば名前が分かるからです。
ところが、この「エトセトラ」に出ている覚え方。
向山の文章は、少し違います。
|
1)桜 千枝。しゃれた名だ。春四月。出会いの相手としては、うってつけだ。
2)向井正子。どこかで聞いた名だぞ。そうそう、お袋の名が向山まさ子というのだ。一字ちがいではないか。
3)五十嵐、栗山。今年卒業させたクラスにもいた。
4)陶山。須山なら前のクラスにいたけどなあ。
5)平 和民。これはすごい名だ。平和を求める市民となるじゃねえか。
6)駒形。芝居にあったなあ。
|
|
このように
|
|
その子の名前をみながら、様々に想いめぐらす
|
というのです。
やったことありますか?
「駒形」と聞いて「芝居」を思い出していますよね。
これは「一本刀土俵入」の「駒形茂兵衛」でしょうか。
私にはとうていスラスラでてこない連想です。
やはり「知の厚み」ですね。
こうして、自分の経験と結びつける。
それは、記憶として一番強固になります。
|
|
エピソード記憶
|
|
として刻まれるからです。
|
 |
| 3 向山の「出会いの定義」 |
|
「エトセトラ」のNo.1は続きます。
|
|
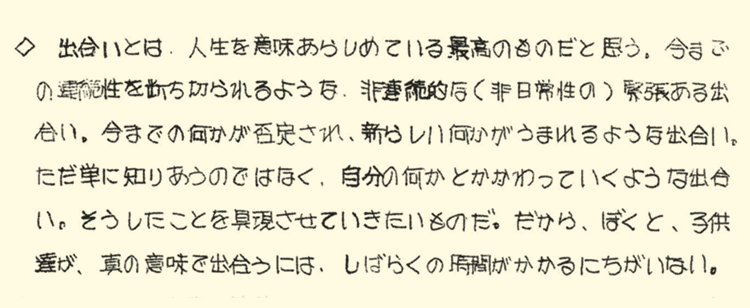
|
|
|
出会いとは、人生を意味あらしめている最高のもの
|
いい言葉ですね。
何の出会いもない人生なんて、考えられません。
どの人もみんな、例外なく、誰かと出会う。
誰かと出会ってこそ、人生にまた別の意味が加わる。
そのくりかえしなのでしょう。
向山は出会いを
|
|
非連続的な(非日常性の)緊張
|
と書いています。
なぜ緊張するかというと
|
|
今までの何かが否定され、新しい何かがうまれる
|
|
というのです。
|
単に知り合うのではなく、
自分の何かとかかわっていくような出会い
|
確かにそうですよね。
大人だってそうです。
単に知り合って名刺交換する。
でも、その後、一切交流がない。
何の変化もしなかった。
そういった出会いもあるにはあります。
でも、
「自分の何かとかかわっていく」
そんな出会いがあったとき、
新しい緊張感が生じ、
新しいアイデアがわき、
新しいチームが生まれ、
新しい仕事が創造される。
そういうこともたくさん経験してきました。
そうした出会いが、今の私の人生をつくってきたとも思えます。
次に続く向山の文が、私には重要だと思えました。
|
だから、ぼくと、子供達が、真の意味で出会うには、
しばらくの時間がかかるにちがいない。
|
明日の出会いは、最初のきっかけにすぎない。
その後に訪れてくるはずの
|
|
真の意味での出会い
|
それは、待っていても訪れてこない。
「今までの何かが否定され、新しい何かがうまれる」
そんな
「緊張ある出会い」
を意図的につくりだしていく。
そういった、向山の決意が表れているように思えます。
自信満々で調子にのっていたころの私には、
そうした決意があっただろうか。
そう振り返らざるをえません。
私に残されたこれからの人生。
それもまた、そうした「緊張」の中にありたいものです。
私は今年61歳になる初老の男です。
それが、31歳の青年教師の文章に今も触発される。
そこから学んでいるということです。
|
 |
| 4 向山の「出会いの存在感」 |
「エトセトラ」のNo.2も見ておきましょう。
No.2の第三段落です。
|
|
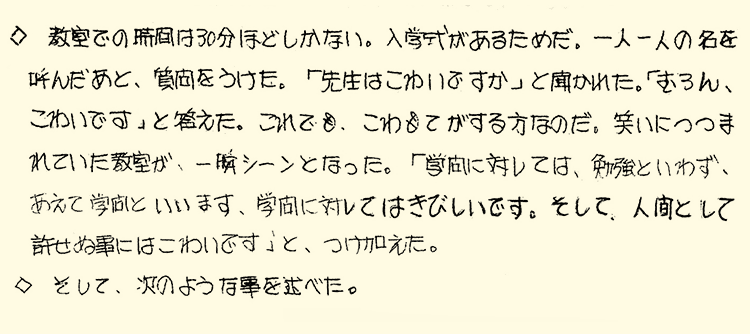
|
「一人一人の名」
それを呼んでいますね。
それから質問を受けています。
この質問のあたりでは
|
|
教師のリズムとテンポ
|
が重要です。
「スピード感」を持ってQAを展開する教師。
子どもたちも新鮮な感覚になります。
気持ちを盛り上げてくれます。
QAで教室は
「笑いにつつまれていた」
とありますね。
この雰囲気がとても大切なのです。
ところが、その質問の中で
「先生はこわいですか」
という質問が出たのです。
向山はそこで、一呼吸おいたのでしょう。
|
|
むろん、こわいです。
|
そこまでのスピード感を殺す。
子どもたち全体に目を合わせる。
そして、ゆったりと言ったに違いありません。
だから教室は
「一瞬シーン」
となるのです。
|
学問に対しては
─ 勉強といわず、あえて学問 ─
といいます。
学問に対してはきびしいです。
そして、人間として許せぬ事にはこわいです。
|
おわかりだと思います。
「きびしい」
「こわい」
この2つを使い分けているのです。
そして、「次のようなことを述べた」とあります。
「次のようなこと」とは?
付録の「えとせとら」をぜひお読みください。
この場面、たまたまかもしれませんが、
|
|
向山からこの話をしはじめたのではない。
|
という点も大切です。
たまたま、
「先生はこわいですか」
の質問が子どもから出た。
それをひきとったのです。
その場で、この展開にしているのです。
その「自然さ」が非常に巧みです。
もちろん、質問は出ないかもしれません。
その場合には、時間をみて質問を打ち切り
|
|
それでは、最初ですから、先生からお話をします。
|
といって始めてももちろんかまいません。
翌日に、別のきっかけから話をしてもかまいません。
いずれにしても初日、遅くとも3日目までには話したい内容です。
それを向山は、子どもの質問から場を見取り、自然に展開しているわけです。
こうした教師の
|
|
初日の存在感
|
|
は非常に重要です。
|
 |
| 5 向山の「優しさ」 |
さて、向山は「きびしくてこわい」という話でした。
そういった、いわば「オーラ」。
それを向山は持っていると思えます。
ところが、一方で、
「とてもとてもとても優しい局面」
も見せるのです。
例えば、その年の転校生、大河原香への対応です。
大河原香は本名です。
オーストラリアからの転校生です。
英語はネイティブの流暢さです。
ですが、日本語はほとんど分かりませんでした。
その大河原について、向山はこう書いています。
出会った直後です。
|
|
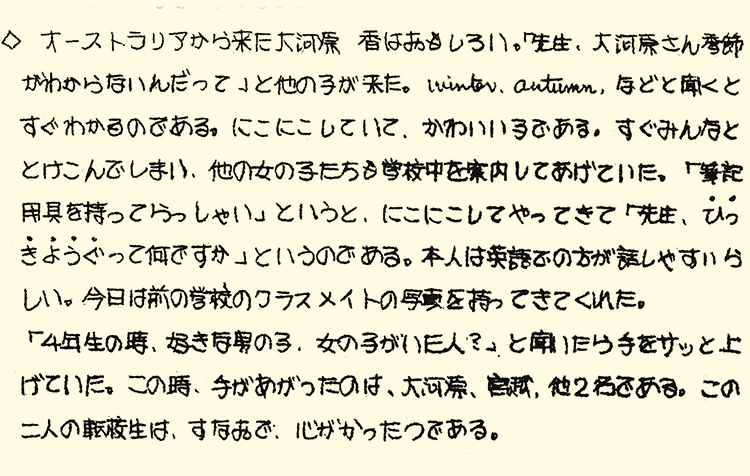
|
「かわいい子である。すぐみんなととけこんでしまい」
と向山は書いています。
さらに
|
にこにこしてやってきて
「先生、ひっきようぐって何ですか」
というのである。
|
でも、このとき、
彼女の内心はドキドキだったようなのです。
大河原ご本人が、後にこう語っているからです。
|
向山先生は、一番最初の授業の終わりに
「じゃあ、みんな明日は筆記用具をもっていらっしゃい」
とおっしゃいました。
その時に、解散しかけているクラスの生徒の間をぬって、わたくしは教壇に近づき、
勇気をふりしぼり、
「先生、ヒッキヨウグってなんですか」
それがはじまりです。
このときに、ニコッと笑われ、
真摯な受け答えをしてくださった向山先生に、
私は2年間、
絶対の信頼をおきました。
|
「勇気をふりしぼり」
って言ってますよね。
本当は不安でいっぱいだった。
そのときの、
|
ニコッと笑われ、
真摯な受け答えをしてくださった
|
という表現。
私は大好きです。
「ヒッキヨウグ」がわからないことに対して、
満面の、しかし自然な笑顔でニコッとしながら、
おそらくは
「とても丁寧な言葉づかい」
で香さんに対応したのだろうと思います。
この大河原香氏。
後に聖心女子学院にすすみました。
社長秘書などを歴任します。
現在は、河野太郎衆議院議員の奥様としても有名です。
(参考HP https://petitwings.com/archives/17708)
|

(向山のエピソードを話す河野香氏 TOSSサマーセミナーにて)
|
|
|
|
出典・引用
1)向山洋一『学級通信エトセトラ No.1』調布大塚小学校5年生 1975年 向山実物資料A111-05-01-01
2)向山洋一『学級通信エトセトラ No.2』調布大塚小学校5年生 1975年 向山実物資料A111-05-01-02
3)向山洋一『学級通信エトセトラ No.3』調布大塚小学校5年生 1975年 向山実物資料A111-05-01-03
関連リンク
1)向山洋一『学級通信スナイパーNo.91』(TOSSメディア)https://lib.tossmedia.jp/246249/book/
閲覧には会員登録、年会費等が必要です。
2)向山洋一『新版続・授業の腕を上げる法則』学芸みらい社,2015年,p.23
3)Feathered News(河野香の学歴&実家)
https://petitwings.com/archives/17708
|
|
|
『谷和樹の教育新宝島』内コンテンツの著作権は、すべて編集・発行元に帰属します。本メルマガの内容の大部分または全部を無断転載、転送、再編集など行なうことはお控えください。
また、当メルマガで配信している様々な情報については、谷本人の実践、体験、見聞をもとにしておりますが、効果を100パーセント保証する訳ではございません。
選択に当たってはご自身でご判断ください。
|
※特典資料ダウンロードページおよび資料や映像、音声は予告なしに削除・変更されることがありますこと、あらかじめご了承ください。