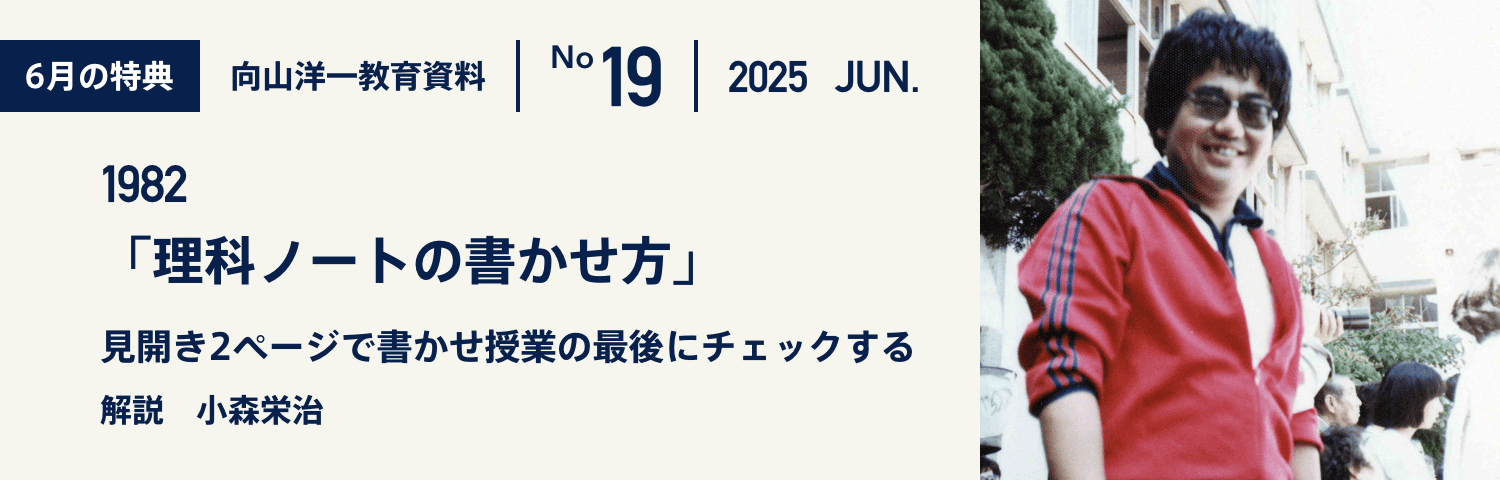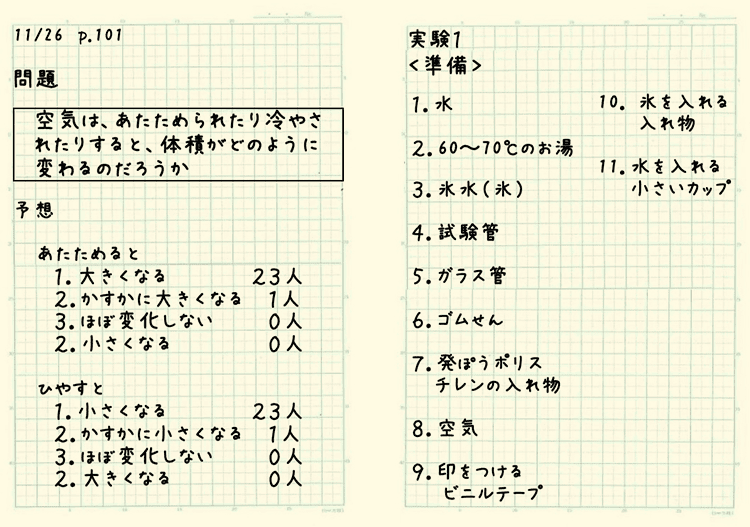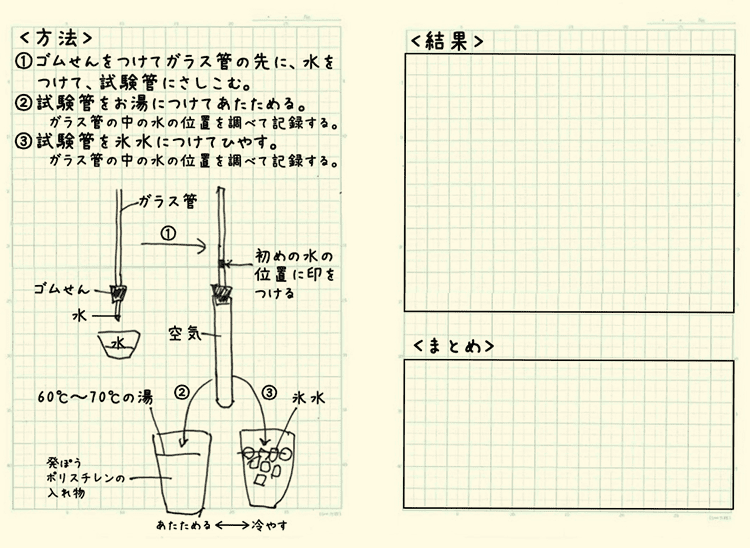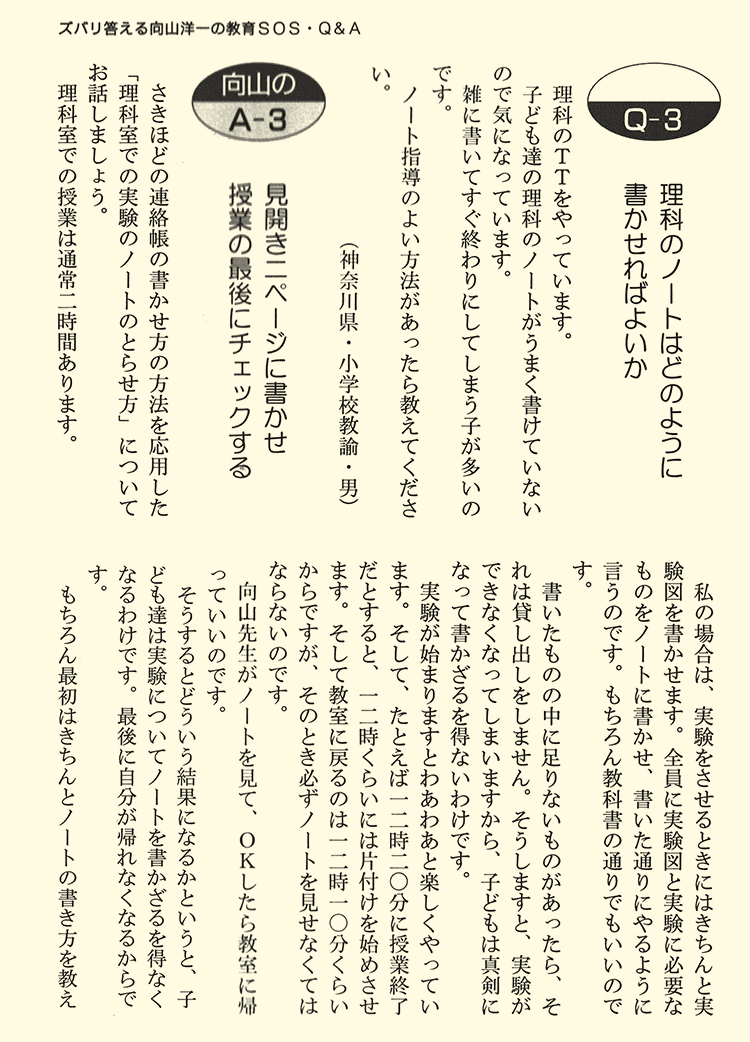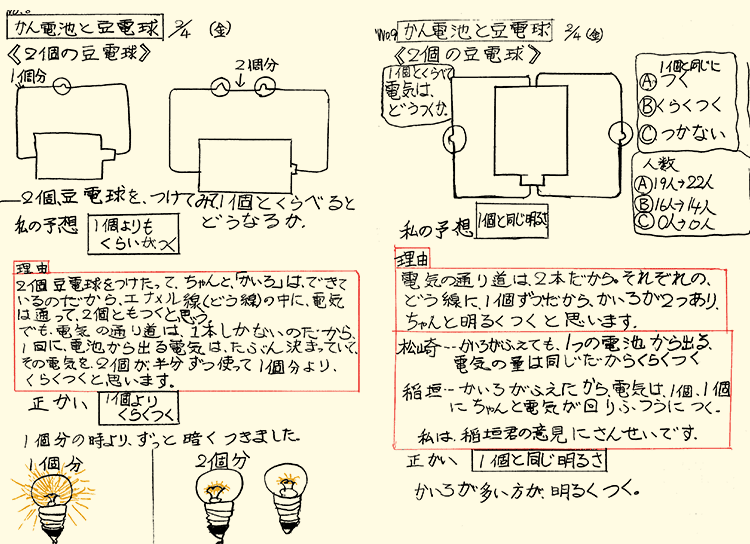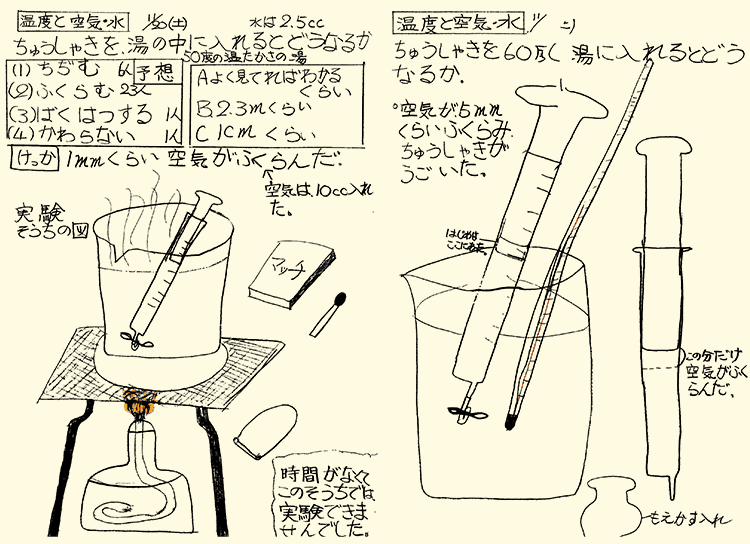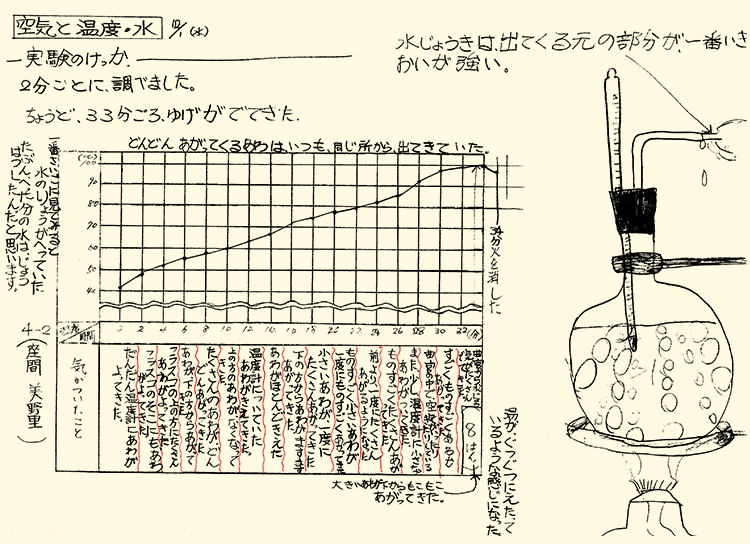この1)から5)を見開き2ページで完結します。
それが理想です。
実験によっては2ページに入らないこともあります。
その場合は上のように4ページ展開で書かせます。
さて、次に最も重要なポイントがあります。
|
|
2 全員のノートをチェックする
|
全員のノートをチェックするのですが、
理科の実験って通常は4人グループ等でやりますよね。
そこで、子どもたちに次のようにいいます。
|
実験図と実験に必要なものをノートに書きなさい。
班で相談しながら書きなさい。
書いた通りに、実験してもらいます。
|
「書いた通りに」
というのがポイントです。
実験図と必要なものは、
「教科書のとおり」
で全く問題ありません。
子どもたちが自分で考えたものでもかまいません。
それは、そのときどきで違います。
|
1)その単元のねらい
2)その単元の内容
3)学校の理科室の備状況
4)子どもたちの実態・・・
|
1学期の最初ごろなら、教科書どおりが安定します。
子どもたちは相談しながら、書きます。
やがて書き終わります。
|
実験図と準備物が書けたら、
班の4人でそろってノートを持っていらっしゃい。
|
4人そろって持ってこなければなりません。
最初の班が4人そろって先生のところにきます。
そこで、教師は「にこやかに」こう言います。
|
じゃ、きびしく!みますね。
太郎ちゃんのノートから見せてください。
|
おわかりですね。
太郎ちゃんはやんちゃな子です。
いいかげんに書いています。
4人そろっていくんだ。
自分がちょっといいかげんでも大丈夫だろう・・・
そうたかをくくって来たのです。
太郎ちゃんは、あせります。
「えっ、ぼくのノート?」
「そうだよ、太郎ちゃんのノート(^^)」
「えっ、ちょっ、ちょっと待って」
そう言って、4人そろって出直してくる班もあります。
「太郎、何やってんだよ」
「ちゃんと書きなさいよ」
班の子たちに言われながら、必死に直してきます。
他の班も次々にやってきます。
「先生できました!」
けっこう自信満々の班もあります。
そこで、こう言います。
|
ここに書いてあるものしか、絶対に貸し出しませんよ。
足りないものがあったら実験できませんが、
本当にだいじょうぶですか?
|
子どもたちは
「ぎくっ」
となります。
「えっ、えーと、先生、ちょっとだけ待ってください」
そう言って、また戻り、再度相談する班もあります。
子どもたちは可愛いですよ。
「空気」とか「ゴミ箱」まで書いてくる班もあります。
4人ともちゃんと書けていた班から合格です。
理科室の授業は2時間連続の学校が多いでしょうか。
でも、1時間の学校もありますよね。
どちらでもかまいません。
2時間連続なら、理科室でノートを書き始めます。
上のノートが合格した班から、実験道具を貸し出します。
1時間なら、ノートは教室で書いてもかまいません。
合格した班から休み時間でもいいですし、
時間が余っているなら、残りの時間で
「植物の観察」などをさせてもかまいません。
その次の時間に、理科室ですぐにスタートできます。
|
 |
| 2 授業が変わる理科ノートシステム(中) |
さて、実験が始まりました。
ノートにすべての準備と実験図が書いてあります。
教師は説明する必要ありません。
(安全面の注意があるときは別ですよ)
子どもたちだけで、どんどん実験が進んでいきます。
教師は、安全面を中心に、各班を見ていればいいだけ。
順調に進んでいるなら、その間に教師は
|
|
この次の時間の実験の準備
|
をしてしまうといいでしょう。
班の数だけトレーを置きます。
その中に次回の実験用具を入れておきます。
子どもたちが本時の実験をしている間に、
次の時間の実験の準備が完了します。
「となりのクラスの分」も準備しておくと喜ばれます。
次の実験の準備って放課後にしたりしませんか?
その必要はほとんどなくなります。
すべて、向山から習いました。
さて、やがて実験が終わる班も出てきます。
その班から、
|
|
3 ノートに結果と考察を書く
|
わけです。
「書くための欄」をあらかじめ作ってあるのですから、
自動的に進みます。
いちいち作業を止めて、静かにさせて、
教師が必死に指示をする必要はありません。
さきほど「教科書どおり」でいいと書きました。
すると、心配される先生がいます。
|
教科書どおりだと、実験の結果がわかってしまって、
つまらないのではありませんか?
|
そんなことはありません。
教科書どおりにやって、教科書どおりの結果が出る。
それを子どもたちはとても喜びます。
熱中して取り組みます。
実際の実験では、ときに「誤差」が出ます。
「先生、教科書に書いてある結果になりません!」
と、相談にくる班もあります。
にこやかに、次のようにいいます。
|
それが実験した結果ですから。
違っていたなら、違っていたことを書きましょう。
|
すると、子どもたちは
「なぜ、違ったんだろう」
と考えるのです。
「先生!もう1回実験をしてもいいですか?」
と言って再チャレンジする班もあります。
|
 |
| 3 授業が変わる理科ノートシステム(後) |
やがて、結果と考察を書き終わります。
ここで、最後のポイントです。
|
|
4 ノートが合格した班から教室に帰る
|
たとえば、12時20分に授業終了だとします。
すると、12時すぎに片付け開始。
12時5分くらいから教室に戻る準備となりますよね。
その際、
|
|
必ず先生にノートを見せなければならない
|
のです。
実験の片付けも点検しますから、これも
「班ごとに4人そろって」
持ってこさせるのがいいでしょう。
さきほどと同じです。
|
じゃ、きびしく!みますね。
どの子のノートから見ようかな。
|
子どもたちはわかってきます。
ちゃんと書くようになります。
ちなみに、4時間目なら、次は給食。
6時間なら次は下校。
いずれも、理科室にくるまえに準備が完了しています。
給食ならランチョンマットや当番着のセット。
下校なら連絡帳は記入済でランドセルと帽子は机の上。
その状態で理科室に来ているわけです。
ノートが合格した班からすぐに帰れるのです。
中堅以上の先生方には初歩的なことですね。
こうしたしくみをちゃんとつくっておけば、子どもたちは混乱なく動きます。
このことを紹介している向山の文章を載せますね。
|